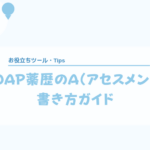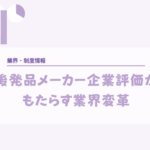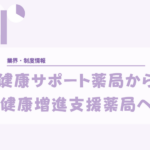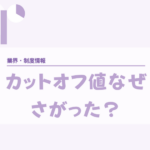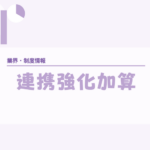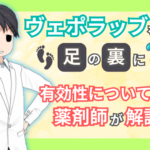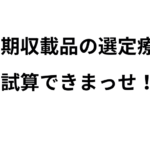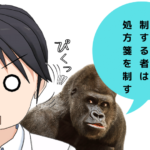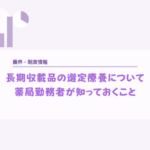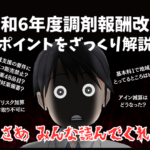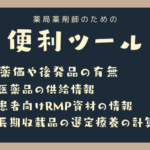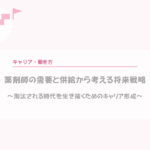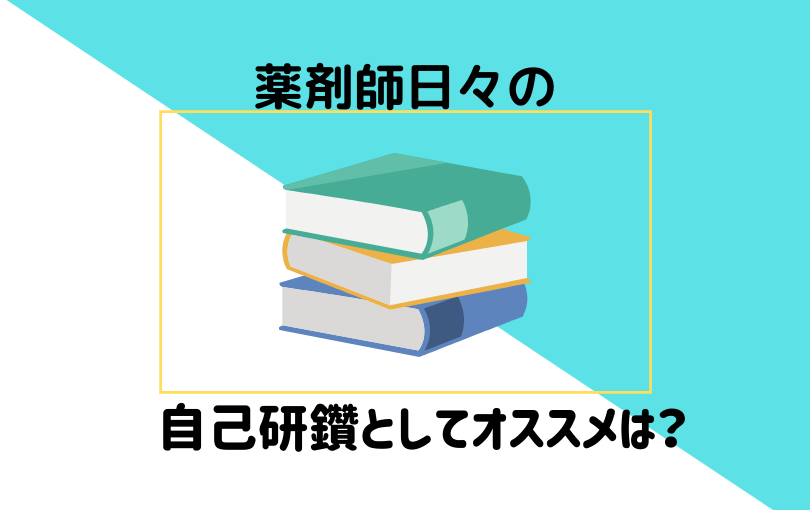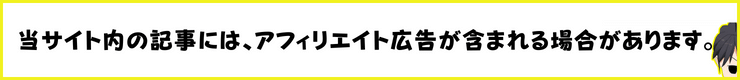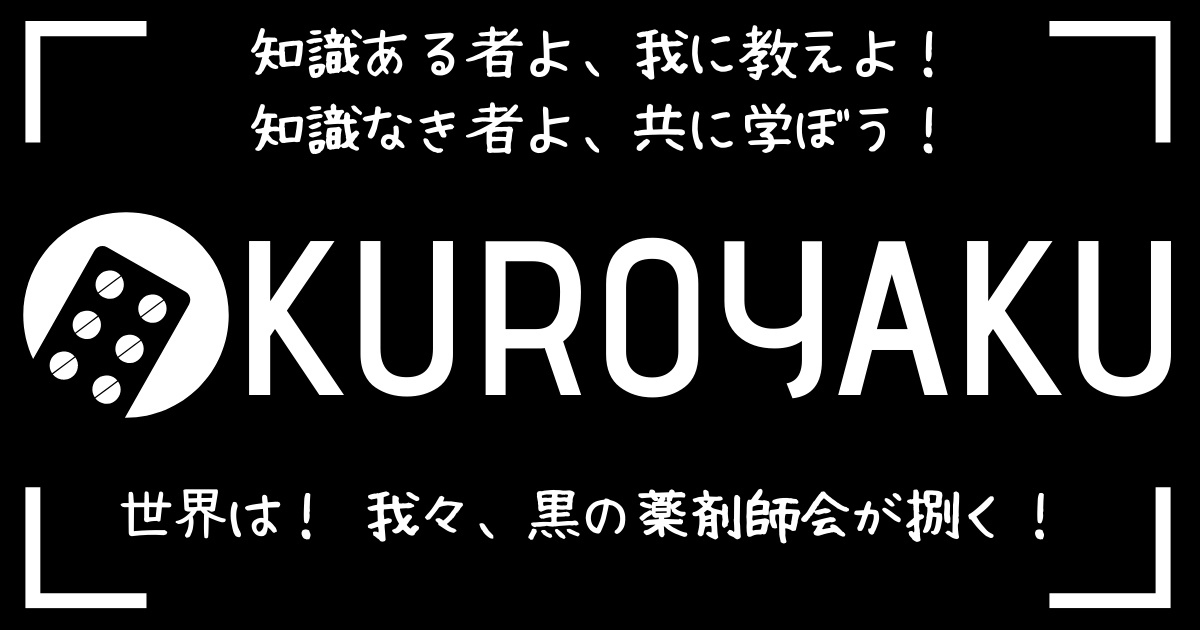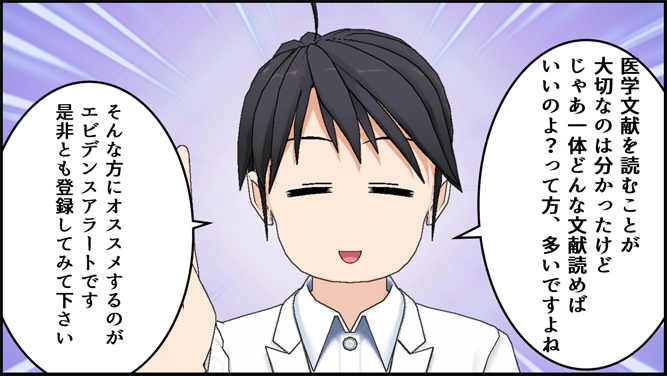薬剤師は、医薬品の専門家として、患者さんや医療チームに対して適切な薬物療法を提供する重要な役割を担っています。そのため、継続的な勉強が求められる職業です。
この記事では、新人薬剤師にオススメの勉強法およびオススメしない勉強法の両方を紹介します。
1_011.png)
1_012.png)
目次
若いうちに必要なスキルについて
私のブログは若手薬剤師(20代~30代)を対象にしているため、どんなことを勉強するといいんだろう?と思う方もいるかもしれません。。
まずオススメしたいのは、コミュニケーション能力です。
対物から対人へと聞き飽きたかもしれませんが、対人業務をしっかり行う上でコミュニケーション能力は欠かせません。
Kim MG, Lee NE, Sohn HS. Gap between patient expectation and perception during pharmacist-patient communication at community pharmacy. Int J Clin Pharm. 2020 Apr;42(2):677-684. doi: 10.1007/s11096-020-01014-3. Epub 2020 Apr 7. Erratum in: Int J Clin Pharm. 2020 Dec;42(6):1539. PMID: 32266556.
この研究は、韓国の地域薬局における薬剤師と患者とのコミュニケーションにおいて、患者の期待と認識のギャップを評価することを目的としています。2018年5月に500人のサンプルを対象に、オンラインまたは書面でのアンケート調査が実施されました。アンケートでは、情報共有とコミュニケーションスキルに関する期待と認識が4点リッカート尺度で評価されました。
460人の回答者のうち、ほとんどの人が薬剤師と情報を共有したいと考えていましたが、期待と認識の間にはすべての項目で有意なギャップが見られました(p < 0.01)。特に、副作用、薬物相互作用、過去の薬物アレルギーに関するギャップスコアが最も高くなりました。また、ギャップスコアは、年齢が50-59歳、60歳以上、および慢性疾患が1つ以上ある場合には、負の関連がありました。さらに、コミュニケーションスキルに関しては、特にプライベートな空間に関する認識が低かったです。
結論として、薬剤師と共有される情報は、参加者の期待よりもかなり少なく、ほとんどの薬剤師のコミュニケーションスキルが不十分であると評価されました。患者中心のコミュニケーションを改善するためには、各患者の期待を理解し、適切なコミュニケーションスキルを用いてコミュニケーションすることが必要です。

ポッポ先生
日本でも同様の結果になりそうですね
またコミュニケーション能力は患者対応だけでなく、他者と働くうえで、心地よく仕事をするためにとても重要です。
たとえば、薬剤師の転職理由の上位に、職場の人間関係というのは入ってきます。もちろんこれは薬剤師は頭がおかしいからという理由ではなく、どの業界でも同じです。
人間関係で悩む理由として、本質的な価値観が異なることとコミュニケーションの方法が合わず、意思疎通が十分にできないこと、この二つが多いです。
本質的な価値観が異なる場合は、コミュニケーション能力で解決はできませんが、後者の場合では、あなたが相手に合わせたコミュニケーション方法を使いこなせれば、無用な人間関係に悩まされなくてすみます。

ポッポ先生
頭おかしい薬剤師もけっこういますからね…
アンガーマネジメントやアサーティブコミュニケーション、あとは北野唯我さんの【タイミングの法則】 【YeS,but構文】 【Helpneeded構文】、【目的ファーストの法則】 【動詞の法則】 【短文の法則】 【共通感情の法則】あたりは学んでおいて損はないと思います。


ポッポ先生
薬剤師も専門スキルの向上ばかり目指さず、ビジネス書も読むのだ
オススメの勉強法・オススメしない勉強法
薬剤師にはコミュニケーション能力が必要だ、というのはおそらく「薬剤師 オススメの勉強法」で検索してきたユーザーの意図を満足させていないと思いますので、意図に合わせたオススメの勉強法、オススメしない勉強法を紹介します。
オススメしない勉強法について
まずはオススメしない勉強法としては、薬局にある医薬品を毎日ひとつずつ添付文書を読んでまとめてみるという方法です。
類似する内容として、今日の治療薬や治療薬マニュアルを毎日1ページ読むとかです。

ポッポ先生
私も何回か「やるぞー」と意気込んでやりました…しかし挫折…
私はあまり長続きするタイプではないから仕方ないかなと思ってましたが、調剤と情報2020年6月号で岸田直樹医師が下記のことを述べていました。
是非、みなさんも処方と病名からここまで深く掘り下げてみてください。
その際に改めて注意ですが、大きな内科の教科書を最初から読むのはやめましょう。あの分厚い内科学の本を全部読んでみたい気持ちはわかります。しかし、挫折への道は100%確定でしょう。医師の世界でも、そのような勉強をしているのを時々みかけ、読破した武勇伝をたまに聞きますが、その背後にそれ以上の挫折者、おそらく90%以上の挫折者がいます。また、読破した医学生が際立って内科学の知識をもっていると思ったことは一度もありません。そのように、読んでも残っているのは達成感だけだったりします。
そのようなアプローチがダメというわけではないのですが,臨床で役立つ知識として大切な方法は,本連載のように1例1例にアプローチすることなのです。服薬指導から出たクリニカルクエスチヨン(臨床上の素朴な疑問)から教科書を開いて,そこを勉強していく。このようなアプローチが極めて実践的で有効です。1日1クリニカルクエスチヨンを目標として,それを一つずつ解決していく,その蓄積のほうが何十倍もの力になります。
調剤と情報 26巻8号 Page1553(2020.06)より引用
医師の世界での、分厚い内科の教科書(おそらくハリソン)と薬剤師の今日の治療薬や治療薬マニュアルを同じにしていいいかは議論の余地があるかもしれませんが私としては同様だと思います。
勉強の目的が達成感を得るためになってしまう可能性があります(大多数は挫折するでしょうが…)
尚、辞書的な本を読み解くのは非効率だからオススメしないと書いていますが、下記の書籍の中では、若手に辞書的な本を読み解く勉強本をオススメしていたので共有します。


ポッポ先生
色々な意見があるってことで
オススメの勉強法は?
それでは続いてオススメの勉強法についてです。
これは上記の岸田医師の引用記事にもある通り、1例1例掘り下げてみることです。
掘り下げるって何?と思うかもしれませんが日々の服薬指導の中で患者さんに質問されたこと、指導した内容への患者さんの反応がいまひとつだったこと、服薬指導してて、この部分ツッコまれたら、うまく答えられないと思ってあまり深入りしなかったことありますよね。
こういった内容をメモ帳などに記録して、あとで調べてみましょう。

ポッポ先生
調べる方法が分からないという方は以下の書籍購入しましょう

また調剤と情報2020年臨時増刊号での宮崎長一郎さんのこの言葉もグッときました。
薬局薬剤師は、薬局という分野で仕事をする専門家である限りは、その仕事には専門性があるといえる。薬局薬剤師には、次のことを肝に銘じてほしい。
専門性を獲得するためには、仕事を計測し、論理性を獲得する作業を日々実施することが大切である。
調剤と情報 26巻7号 Page1336(2020.06)より引用

ポッポ先生
問いをたて、その問いの解決方法を調べるということを日々行うことが薬剤師として重要だなと思います。
なので、問いの立て方、疑問の解決方法などは早い段階で理解しておくことが大切です。
オマケ:日々論文を身近にしておくことも重要
これからの対物から対人へということで、対人業務の能力開発は必須です。
下記記事でも紹介しているように、医師の半数近くは薬剤師に大規模な臨床研究の結果などは知っておいてもらいたいと思っています。
医療において、重要な情報はまず英語で情報発信されます。その情報を基に一部、日本語の情報サイトやわたしのようなブロガーが取り上げたりしますが、情報のタイムラグや内容の改変を減らすためには英語で一次情報を入手できるようにしておいたほうがいいです。

ポッポ先生
我々世代で読んでいる人は少ないですが、これからの薬剤師には英語の医学論文を読める力は必要だと思います。
そこで医学論文を身近にするために、エビデンスアラートを登録しておいてはいかがでしょうか?
登録しておくと、話題の論文がメールで届くので、受け身で最低限の情報を入手することができます。是非とも以下の記事を参考に登録してみてください。(無料です)
まとめ
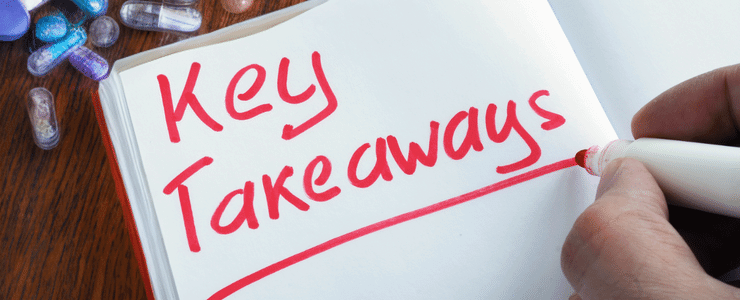
今回は薬剤師のためのオススメの勉強法、オススメしない勉強法について紹介しました。
オススメしない勉強法として、分厚い本の熟読などを挙げましたが、自己肯定感の低い薬剤師にとっては達成感を得て自信を持つようになるからいいのかもしれません。
ただ達成できない人が大多数だと思いますので、できなくても自信をなくさなくて大丈夫です。
オススメの勉強法としては、日々出会った臨床疑問をそのままにせず、しっかりと調べる癖をつけまよう。

ポッポ先生
疑問を持たないと成長は難しいので、問いを立てる力はしっかりと身につけてほしいです。
ChatGPTのようなAIが今後、大きく発展してくると思います。その中で必要になってくるのはコミュニケーション能力および問題を見つける能力なのではないかと思います。
スキルは一朝一夕で身につくものではないので早い段階から日々、戦略を立てて学んでいくのがよいのではないでしょうか。