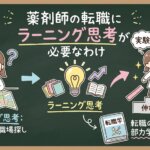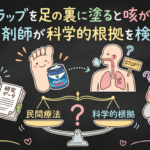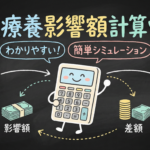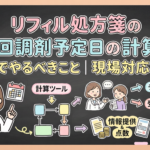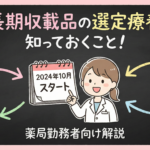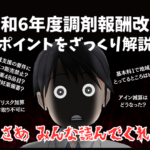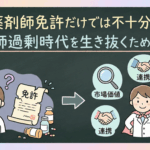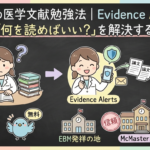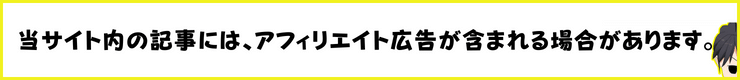目次
特定薬剤管理指導加算1とは?薬局薬剤師が知っておくべき基本情報

特定薬剤管理指導加算1とは、ハイリスク薬(特に安全管理が必要な医薬品)が処方された患者さんに対して、通常の服薬指導に加えて特別な薬学的管理や指導を行った場合に算定できる加算です。処方箋を応需する薬局薬剤師にとって、日常業務で頻繁に関わる重要な加算制度となっています。
薬剤師の専門的な知識と技術を活かした対人業務の評価として、2010年度の診療報酬改定で新設されました。適切な服薬管理と副作用モニタリングを通じて患者さんの安全を守る重要な役割を担っています。

ポッポ先生
ハイリスク薬は適正使用ができていないと患者さんに大きな健康被害を及ぼす可能性があります。そのため、薬剤師の専門的な薬学的管理と指導が特に求められるのです!
ハイリスク薬って聞くと難しそうですが、具体的にはどんな薬が対象になるんですか?

オカメインコ
令和6年度(2024年度)改定の重要ポイント

2024年度の調剤報酬改定では、特定薬剤管理指導加算1に関して重要な変更がありました。主な改定ポイントは以下の通りです
- 算定区分の明確化: 「イ」と「ロ」の2区分に分けられ、それぞれに異なる点数が設定されました
- イ:ハイリスク薬が新たに処方された患者に対して必要な指導を行った場合(10点)
- ロ:ハイリスク薬の用法・用量の変更や副作用の発現状況等に基づき、薬剤師が必要と認めて指導を行った場合(5点)
- 指導対象薬剤の範囲変更: 以前は複数のハイリスク薬が処方されている場合、「全て」について必要な指導を行う必要がありましたが、改定後は「薬剤師が必要と認める」ものについて指導を行えばよいことになりました
- 新規加算の追加: 特定薬剤管理指導加算3が新設され、RMP資材を用いた指導や医薬品選択に関する説明などが評価されるようになりました

ポッポ先生
これまでの「ベタ取り」のような算定はできなくなりましたが、薬剤師の専門的判断を尊重した改定となっています。対象薬が複数ある場合も、薬剤師が必要と判断した薬剤について指導すればよくなりました!
特定薬剤管理指導加算1の算定要件を詳しく解説

算定の基本条件
特定薬剤管理指導加算1を算定するための基本的な条件は以下の通りです
- 服薬管理指導料またはかかりつけ薬剤師指導料を算定している
- 厚生労働大臣が定める「特に安全管理が必要な医薬品」が処方されている
- 当該薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を患者または家族に伝えている
- これまでの指導内容等も踏まえ、適切な服薬指導を行っている
「イ」の算定要件(10点)
「イ」は、ハイリスク薬が新たに処方された患者に対して必要な指導を行った場合に算定できます。以下の点に注意が必要です:
- 「新たに処方された」とは、その患者さんにとって初めて処方された場合を指します
- 患者さんが他の薬局で継続服用している薬であれば、当該薬局で初めて調剤する場合でも「イ」は算定できません
- 同一成分の単なる銘柄変更(例:トーワ→サワイなど)の場合は算定できません
「ロ」の算定要件(5点)
「ロ」は、以下のいずれかの条件を満たす場合に算定できます
- ハイリスク薬の用法または用量が変更された場合
- 患者の副作用の発現状況に変化があった場合
- 服薬状況などに変化があり、薬剤師が必要と認めて指導を行った場合
副作用が発現している場合や服薬状況に問題がある場合など、薬剤師が必要と判断して特別な指導を行った場合に算定できます。

ポッポ先生
「イ」と「ロ」は同時算定できません!同一処方箋内で「イ」と「ロ」の両方に該当する薬剤があっても、どちらか一方のみの算定となります。その場合は、点数の高い「イ」の算定をお勧めします!
対象となるハイリスク薬の範囲

特定薬剤管理指導加算1の対象となる「特に安全管理が必要な医薬品」は、厚生労働省によって定められています。主な対象薬剤カテゴリーは以下の通りです
- 抗悪性腫瘍剤(注射薬、内服薬、外用薬)
- 免疫抑制剤(臓器移植時の拒絶反応抑制目的で用いるもの)
- 不整脈用剤(注射薬、内服薬)
- 抗てんかん剤(注射薬、内服薬)
- 血液凝固阻止剤(注射薬、内服薬)
- ジギタリス製剤(注射薬、内服薬)
- テオフィリン製剤(注射薬、内服薬)
- カリウム製剤(注射薬、内服薬)(経口カリウム製剤については、常用量の患者に対し投与する場合に限る)
- 精神神経用剤(注射薬、内服薬)(抗精神病薬、抗うつ薬、抗躁薬に限る)
- 糖尿病用剤(インスリン製剤等、スルホニルウレア剤、ビグアナイド系製剤、チアゾリジン系製剤、SGLT2阻害剤、DPP-4阻害剤、GLP-1受容体作動薬)
- 膵臓ホルモン剤(膵臓ホルモン、インクレチン)
- 抗HIV薬
糖尿病の薬も多く含まれているんですね!でも同じ薬でも使う目的によって算定できないこともあるんですか?

オカメインコ

ポッポ先生
その通りです!例えばメインテートなら不整脈に対して処方されている場合は算定対象ですが、高血圧症や狭心症に対しての処方なら対象外です。フォシーガも糖尿病治療目的なら算定できますが、心不全や腎臓病に対しての処方では算定できません。処方目的の確認が重要です!
特定薬剤管理指導加算1の算定上の注意点

特定薬剤管理指導加算1を算定する際の主な注意点は以下の通りです
- 処方箋受付1回につき1回のみ算定可能:同一処方箋でハイリスク薬が複数あっても、加算は1回のみ
- 「イ」と「ロ」の併算定不可:同一処方箋内で「イ」と「ロ」に該当する薬剤がある場合、どちらか一方のみ算定
- 対象疾患の確認:複数の適応がある薬剤は、処方目的が特定薬剤管理指導加算の対象となる適応症か確認が必要
- 薬歴への記載:対象となる医薬品が分かるように記載し、確認した内容や指導の要点を記録
- 他の加算との併算定:特定薬剤管理指導加算3との併算定は可能だが、特定薬剤管理指導加算2の対象薬剤については、同一月内での特定薬剤管理指導加算1との併算定はできない

ポッポ先生
薬歴への記載は非常に重要です!対象となる医薬品名、確認した内容(副作用の有無、服用状況など)、行った指導の要点を具体的に記録しましょう。
服薬指導のポイントと具体的な確認事項

ハイリスク薬の服薬指導では、日本薬剤師会の「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」を参考に、以下のような確認・指導を行いましょう。
全てのハイリスク薬に共通する確認事項
- 処方内容の確認:薬剤名、用法・用量、投与期間等
- アドヒアランスの確認:服薬状況、飲み忘れ時の対応確認
- 副作用モニタリング:副作用の有無、対処方法の説明
- 効果の確認:薬剤の効果が得られているか
- 相互作用の確認:併用薬、OTC薬、サプリメント、食事等との相互作用
薬効群別の確認事項(例)
血液凝固阻止剤の場合
- 出血傾向(歯肉出血、鼻出血、皮下出血、血尿、黒色便など)の有無
- ビタミンK含有食品(納豆、クロレラ、青汁など)の摂取状況
- 併用注意薬(NSAIDs、抗菌薬など)の使用状況
糖尿病用剤の場合
- 低血糖症状(冷や汗、動悸、手の震え、空腹感など)の有無
- 血糖値の自己測定結果(実施している場合)
- シックデイの対応方法の理解度
服薬指導のときに何を確認すればいいか分からないときは、このガイドラインを参考にするといいんですね!

オカメインコ
実践!特定薬剤管理指導加算1の算定事例

事例1:新規処方の場合(「イ」算定)
処方内容:グリメピリド1mg 1日1回朝食後 28日分(糖尿病治療薬)
状況:初めて2型糖尿病と診断され、経口血糖降下薬が処方された患者
服薬指導のポイント
- グリメピリドがハイリスク薬であることを説明
- 低血糖症状とその対処法について詳しく説明
- 食事・運動療法の重要性を説明
- 飲み忘れた場合の対応方法を説明
- 定期的な血糖検査の重要性を説明
算定:特定薬剤管理指導加算1「イ」(10点)
事例2:副作用発現時の対応(「ロ」算定)
処方内容:ワーファリン1mg 1日1回夕食後 28日分(抗凝固薬)
状況:継続服用中の患者が「最近歯磨きのときに歯茎から血が出やすい」と訴えた
服薬指導のポイント
- 出血傾向の詳細(頻度、程度、部位など)を確認
- 他の出血症状(鼻血、皮下出血など)の有無を確認
- 食事内容の変化(納豆、青汁などの摂取)の有無を確認
- 併用薬の変更(市販のNSAIDsの使用など)の有無を確認
- 必要に応じて医師への情報提供を検討
算定:特定薬剤管理指導加算1「ロ」(5点)

ポッポ先生
副作用が疑われる症状がある場合は、自己判断で服薬を中止せず、必ず医師や薬剤師に相談するよう患者さんに伝えることが大切です!また、必要に応じて処方医への情報提供も積極的に行いましょう。(服薬情報等提供料2の算定)
まとめ:薬剤師として特定薬剤管理指導加算1への対応を考える

特定薬剤管理指導加算1は、ハイリスク薬を服用する患者さんの安全を守るための重要な薬学的管理・指導を評価する加算です。2024年度の改定では算定区分が明確化され、薬剤師の専門的判断を尊重した内容となりました。
薬剤師として以下の点を心がけましょう
- ハイリスク薬の薬効群と対象疾患を正確に把握する
- 患者さんの状態に応じた適切な服薬指導を行う
- 副作用モニタリングとその対処法について丁寧に説明する
- 薬歴に確認・指導内容を具体的に記録する
- 処方医との積極的な連携を図る
ハイリスク薬の安全使用において薬剤師の果たす役割は非常に大きいものです。患者さん一人ひとりの状況に合わせた丁寧な服薬指導を通じて、医薬品の適正使用と患者さんの安全確保に貢献していきましょう。
特定薬剤管理指導加算1の算定要件がよく分かりました!これからハイリスク薬の服薬指導をするときは、患者さんの安全を第一に考えて丁寧に説明していきたいと思います!

オカメインコ
参考資料:
- 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和6年3月5日 保医発0305第4号)
- 疑義解釈資料の送付について(その1)(令和6年3月28日)
- 薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン(第2版)(日本薬剤師会)
- 特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧(厚生労働省)