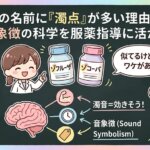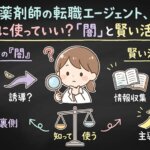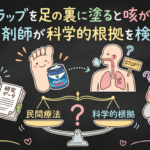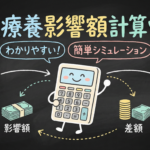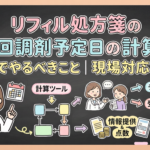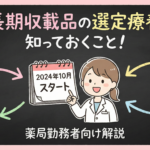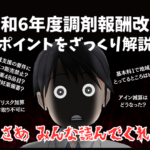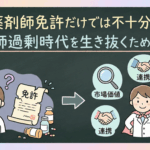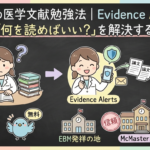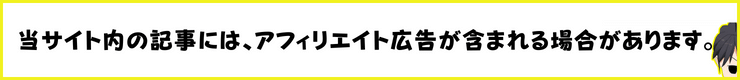ポリファーマシー(多剤併用)の問題に対する取り組みが医療現場で注目されている今、薬局薬剤師による減薬提案の重要性はますます高まっています。その中核となる評価項目が「服用薬剤調整支援料1」です。今回は、算定要件から具体的な運用方法まで、現場で即実践できるポイントをご紹介します。
目次
ポリファーマシー解消の鍵!服用薬剤調整支援料1とは
服用薬剤調整支援料1は、ポリファーマシー解消に向けた薬剤師の積極的な取り組みを評価する項目です。2018年度の調剤報酬改定で新設され、2020年度改定では評価体系が見直されて現在の形となりました。その本質は、薬局薬剤師が処方医へ減薬の提案を行い、実際に処方薬が減少したことを評価するものです。

ポッポ先生
服用薬剤調整支援料1は、薬剤師がポリファーマシー解消のために処方医へ能動的に働きかけ、「成果」として薬剤数が減少した場合に算定できる点数です。薬剤師の専門性が活きる重要な評価項目なのです!
薬剤師による対人業務の質の向上が求められる中、この項目は単なる点数以上の意味を持ちます。ポリファーマシーに関連する有害事象の防止や患者さんのQOL向上、医療費適正化といった多面的な意義があるのです。
服用薬剤調整支援料1の算定要件を徹底解説

基本的な算定要件
服用薬剤調整支援料1の算定には、以下の条件をすべて満たす必要があります:
- 対象患者: 内服を開始して4週間以上経過した内服薬が6種類以上処方されている患者
- 減薬提案: 患者の意向を踏まえ、服薬アドヒアランスや副作用の可能性を検討した上で処方医に減薬の提案を行う
- 減薬結果: 内服薬の種類数が2種類以上減少(うち少なくとも1種類は薬剤師が提案したもの)
- 継続確認: 減薬状態が4週間以上継続していることを確認
6種類以上の薬を飲んでいる患者さんが対象なんですね!でも内服薬の「種類数」ってどう数えるんですか?

オカメインコ

ポッポ先生
良い質問ですね!内服薬の種類数は、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、液剤については、1銘柄ごとに1種類とカウントします。ただし、屯服薬や服用開始後4週間以内の薬剤、浸煎薬、湯薬は内服薬の種類数に含めません。正確にカウントすることが大切です!
点数と算定回数
服用薬剤調整支援料1は125点(1,250円)で、月に1回に限り算定可能です。また、同一薬局で1年以内に算定した場合は、前回算定時に減少した後の内服薬の種類数からさらに2種類以上減少したときに限り、新たに算定できます。
算定除外のケース
以下の場合は算定できませんので注意が必要です:
- 特別調剤基本料Bを算定している保険薬局
- 重複投薬等の解消に係る提案を行い、服用薬剤調整支援料2を算定した後に、服用薬剤調整支援料1の要件を満たした場合
服用薬剤調整支援料1と服用薬剤調整支援料2の違い

この2つの支援料は、ポリファーマシー解消への取り組みを評価する点では共通していますが、重要な違いがあります。
| 項目 | 服用薬剤調整支援料1 | 服用薬剤調整支援料2 |
|---|---|---|
| 点数 | 125点 | イ:110点/ロ:90点 |
| 評価対象 | 減薬の「結果」 | 減薬の「提案」 |
| 要件 | 内服薬が2種類以上減少し4週間以上継続 | 重複投薬等の解消に係る提案を行った場合 |
| 算定タイミング | 減薬状態が4週間以上継続した後 | 提案書を送付した際の薬剤服用歴の記録又は情報提供に係る記録に記載した保険医療機関への情報提供を行った場合 |
🦜 オカメインコさん なるほど!服用薬剤調整支援料1は実際に減薬された「結果」、服用薬剤調整支援料2は「提案」そのものを評価するんですね!
服用薬剤調整支援料1の算定プロセス

STEP1:対象患者の抽出
薬歴や処方内容から、内服薬が6種類以上処方されている患者さんを抽出しましょう。処方薬の種類数を正確に把握することが第一歩です。
STEP2:減薬の必要性の検討
患者さんの治療状況、副作用発現の可能性、重複投薬の有無などを薬学的に評価します。単に「薬が多い」という理由だけでなく、薬学的な観点から減薬の必要性を検討しましょう。
STEP3:患者の意向確認
減薬の提案には患者さんの同意が不可欠です。服薬状況や体調の変化、服薬に対する考えなどを丁寧に聴取し、患者さん自身が減薬に前向きであることを確認します。

ポッポ先生
患者さんの意向確認は非常に重要です!「薬の数を減らしたいと思いますか?」と直接的に聞くのではなく、「お薬を飲むのは大変ではないですか?」「気になる症状はありませんか?」など、患者さんの本音を引き出す聞き方を工夫しましょう。
STEP4:処方医への提案
検討結果と患者さんの意向を踏まえ、処方医へ減薬の提案を行います。提案は文書で行い、薬剤選択の根拠や期待される効果、患者さんの意向なども明記すると採用されやすくなります。
STEP5:減薬結果の確認
提案後、実際に処方が変更されたか確認します。内服薬が2種類以上減少し、そのうち少なくとも1種類は薬剤師が提案したものである必要があります。
STEP6:減薬状態の継続確認
減薬された状態が4週間以上継続していることを確認します。この継続確認ができて初めて服用薬剤調整支援料1を算定できます。
STEP7:記録と算定
算定の際は、減薬の提案を行った年月日、保険医療機関名、調整前後の薬剤種類数を調剤報酬明細書の摘要欄に記載します。また、薬歴への記録も忘れずに行いましょう。
服用薬剤調整支援料1を算定するための実践的なポイント

1. 日常業務での意識づけ
処方箋を受け付けた際、自動的に内服薬の種類数をチェックする習慣をつけましょう。薬歴システムなどを活用し、6種類以上の内服薬が処方されている患者さんを抽出しやすい環境を整えることも有効です。
2. 効果的な処方医への提案方法
提案書は簡潔かつ根拠を明確にして作成します。「この薬を減らしてください」という指示的な表現ではなく、「このような理由で、〇〇の減量をご検討いただけますでしょうか」といった提案型の表現を心がけましょう。
処方医の先生に提案するのって緊張しますね。どうやったら受け入れてもらいやすいですか?

オカメインコ

ポッポ先生
良い質問です!提案書には「何を」「なぜ」「どうすれば良いか」を明確に記載しましょう。例えば「睡眠薬Aと睡眠薬Bが併用されていますが、同効薬の重複になっています。患者さんからは睡眠の質に不満がないとのことで、睡眠薬Aの中止をご検討いただけますでしょうか」というように具体的に書くことがポイントです!
3. 患者さんとの信頼関係構築
減薬の提案は、患者さんとの信頼関係があってこそ効果的です。日頃から丁寧な服薬指導を心がけ、患者さんが本音を話せる関係性を築きましょう。
4. 多職種連携の活用
医師、看護師、ケアマネジャーなど多職種との連携も重要です。特に在宅医療の場面では、多職種カンファレンスなどで減薬の必要性について話し合うことで、提案が受け入れられやすくなります。
5. 薬歴への記録の充実
提案内容や患者さんの意向、提案に至った経緯などを詳細に薬歴に記録しておくことが大切です。記録が充実していれば、次回の提案や他の薬剤師への引き継ぎもスムーズになります。
実際の算定例から学ぶ服用薬剤調整支援料1

ケース1:同効薬の重複解消による減薬
70代男性、高血圧と不眠症で内服薬8種類服用中。睡眠薬が2種類処方されていることに着目し、患者さんの睡眠状況を確認したところ、「寝つきも良く、途中で目が覚めることもない」とのこと。医師に睡眠薬の重複を指摘し、1剤の中止を提案。結果、処方が見直され、睡眠薬が1種類に減少しました。
ケース2:副作用懸念による減薬
80代女性、複数の慢性疾患で内服薬12種類服用中。最近、ふらつきがあり転倒しそうになると相談があり、降圧剤と抗不安薬の併用による相乗的な血圧低下を懸念。血圧値も安定していることから、降圧剤の減量と抗不安薬の漸減中止を医師に提案。結果、2種類の薬剤が減量・中止となり、ふらつき症状も改善しました。

ポッポ先生
このように、単に「薬が多い」という理由だけでなく、重複投与の解消や副作用の懸念など、薬学的な視点からの具体的な提案が大切です。患者さんの状態をよく観察し、根拠を持って提案しましょう!
服用薬剤調整支援料1の算定における注意点

同一処方内容での重複算定に注意
服用薬剤調整支援料1に係る提案を行った直後に受け付けた当該処方医の発行した処方箋について、提案内容と同一の処方内容の場合は、重複投薬・相互作用等防止加算、在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料は算定できません。
過去の算定履歴の確認
同一薬局で1年以内に服用薬剤調整支援料1を算定している場合は、前回算定時に減少した後の内服薬の種類数からさらに2種類以上減少したときに限り、新たに算定できます。過去の算定履歴を確認することが重要です。
減薬状態の継続確認を忘れずに
減薬された状態が4週間以上継続していることの確認は必須です。減薬直後に算定するのではなく、4週間以上の継続を確認してから算定するようにしましょう。
4週間後にまた来局してもらわないといけないんですか?そのタイミングで処方箋がなかったらどうすればいいんですか?

オカメインコ

ポッポ先生
良い質問ですね!必ずしも来局時の確認でなくても、電話での確認でも構いません。また、お薬手帳への記録を見せてもらったり、次回の処方箋で確認したりする方法もあります。4週間以上の継続確認ができた時点で算定するというのがポイントです!
今後の展望:服用薬剤調整支援料の重要性
ポリファーマシー対策は、今後の医療において重要なテーマとなっています。高齢化社会の進展に伴い、複数の疾患を持つ患者さんが増加する中、適切な薬物療法の提供は薬剤師の重要な責務です。
服用薬剤調整支援料は単なる点数項目ではなく、薬剤師の臨床的な介入とその成果を評価する重要な指標です。また、地域支援体制加算の算定要件にも含まれており、薬局の機能評価にも直結しています。
今後も薬剤師による対人業務の重要性は高まり続けるでしょう。患者さん一人ひとりに適した薬物療法の提供に向けて、積極的に減薬提案を行っていくことが求められています。
まとめ:薬剤師として服用薬剤調整支援料1への対応を考える

服用薬剤調整支援料1は、薬剤師の専門性を活かした対人業務の成果を評価する重要な項目です。算定そのものを目的とするのではなく、患者さんにとって本当に必要な薬物療法を提供するという視点を持ち、日々の業務に取り組むことが大切です。
具体的な取り組みとしては:
- 処方箋受付時に内服薬の種類数を確認する習慣をつける
- 患者さんとの対話を通じて服薬状況や体調変化を丁寧に聴取する
- 薬学的な視点から減薬の必要性を検討し、根拠を持って医師に提案する
- 減薬後の状態を継続的にフォローし、患者さんのQOL向上に貢献する
こうした取り組みを積み重ねることで、薬剤師としての専門性を高め、地域医療における薬局・薬剤師の価値をさらに高めていくことができるでしょう。

ポッポ先生
最後に一つアドバイスを!服用薬剤調整支援料の算定は「結果」ですが、大切なのは患者さんに最適な薬物療法を提供するというプロセスです。点数算定だけを目的にするのではなく、患者さんの健康と安全を第一に考えた取り組みを続けていきましょう!