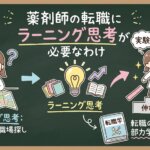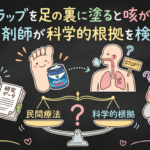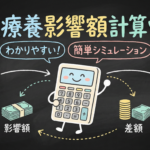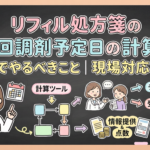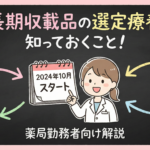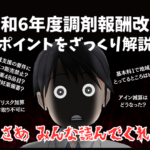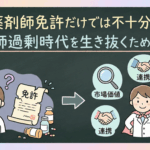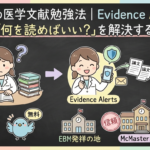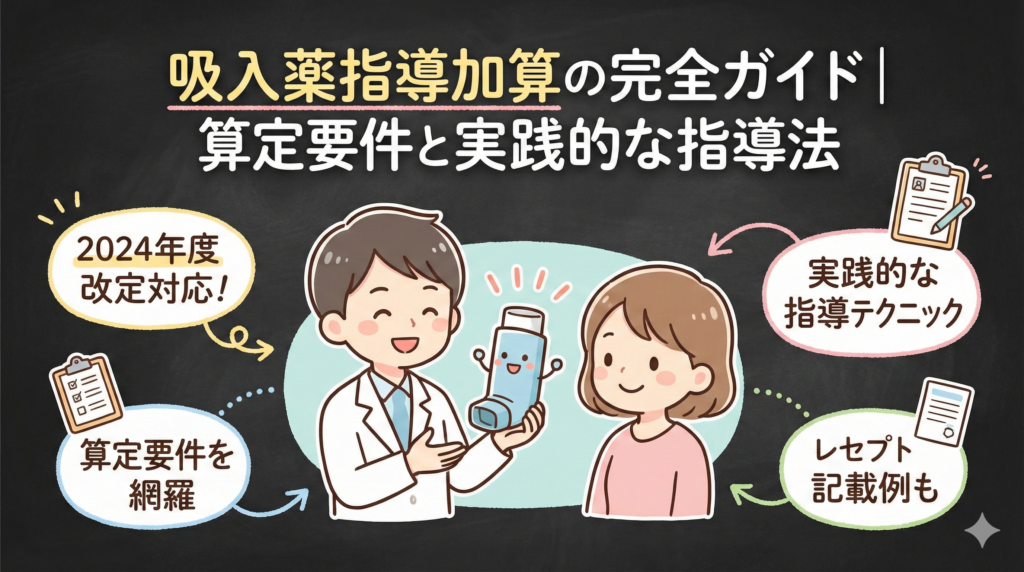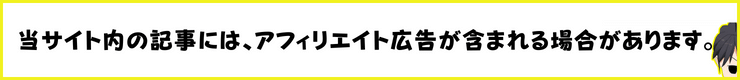吸入薬の適切な使用は治療効果に大きく影響する一方で、多くの患者さんが正しい吸入手技を習得することに苦労しています。そこで重要となるのが薬剤師による吸入指導です。本記事では、2024年度調剤報酬改定で見直された「吸入薬指導加算」について、算定要件から実践的な指導方法までを解説します。
目次
吸入薬指導加算とは?基本情報と2024年度改定のポイント
吸入薬指導加算は、喘息または慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者さんに対して、文書と練習用吸入器を用いた指導を行い、医療機関へ情報提供した場合に算定できる加算です。2020年度の調剤報酬改定で新設され、薬局における対人業務評価の充実を図る取り組みの一環として位置づけられています。

ポッポ先生
吸入薬指導加算は1回30点と決して高くはありませんが、吸入薬を使用する患者さんの治療効果向上に直結する重要な加算です。また、地域支援体制加算の実績要件にも関わるため、積極的に取り組むことをお勧めします!
2024年度改定のポイント
2024年度の調剤報酬改定では、吸入薬指導加算について重要な見直しが行われました。主な変更点は以下の通りです
- かかりつけ薬剤師指導料との併算定が可能に:改定前はかかりつけ薬剤師指導料を算定している患者さんには吸入薬指導加算を算定できませんでしたが、2024年度改定からは算定可能になりました。かかりつけ薬剤師による介入が成果を上げていることが評価されたことによる変更です。
なぜ以前はかかりつけ薬剤師指導料と併算定できなかったのですか?

オカメインコ

ポッポ先生
以前は吸入薬指導がかかりつけ薬剤師の通常業務の一環と考えられていたからです。しかし、吸入薬指導は特別な知識と時間を要する業務であり、かかりつけ薬剤師による専門的な介入が患者さんの治療効果向上に貢献していることが認められ、2024年度改定で併算定できるようになりました!
吸入薬指導加算の算定要件

基本的な算定要件
吸入薬指導加算(30点)の算定要件は以下の通りです
- 対象患者: 喘息または慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者で吸入薬が処方されている方
- 指導の同意: 患者または家族等からの求めがあった場合、または保険医療機関からの求めがあった場合に、患者の同意を得たうえで実施
- 指導内容: 文書および練習用吸入器等を用いた吸入手技の指導と確認
- 情報提供: 保険医療機関に対し、吸入指導の結果等を文書により情報提供すること(お薬手帳による提供も可)
- 算定頻度: 3月に1回に限り算定可能(ただし、他の吸入薬が処方され別途指導を行った場合は3月以内でも算定可能)
除外規定
以下の場合は吸入薬指導加算を算定できません
- 特別調剤基本料Bを算定している保険薬局の場合
- 特別調剤基本料Aを算定している保険薬局が、不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関(敷地内医療機関など)へ情報提供を行う場合
同時算定できない薬学管理料
吸入薬指導加算を算定した場合、下記の薬学管理料は同時に算定できません
- 服薬情報等提供料(吸入指導に関するもの)
吸入薬指導加算の算定手順とポイント

STEP1:対象患者の確認
喘息またはCOPDの患者さんで吸入薬が処方されている方が対象です。処方箋や薬歴から対象となる患者さんを抽出しましょう。
STEP2:医師の了解・患者の同意の確認
吸入薬指導加算の算定には、以下のいずれかの条件を満たす必要があります
- 保険医療機関からの求めがあった場合
- 患者または家族等からの求めがあった場合等で、医師の了解を得たとき

ポッポ先生
医師の了解を得るのがネックになりやすいポイントです。事前に近隣の医師と吸入指導について話し合いをしておくと、スムーズに進められますよ。例えば、「吸入指導希望」など処方箋に記載してもらえるように依頼しておくと便利です!
STEP3:文書と練習用吸入器による指導
吸入指導は必ず「文書」と「練習用吸入器等」を用いて行う必要があります。口頭のみの指導では加算は算定できません。
使用できる資材
- 薬剤に添付されている説明文書
- 製薬会社が提供している吸入指導用資材
- 練習用吸入器(デモ器)
デモ器はどこから入手すればいいんですか?

オカメインコ

ポッポ先生
デモ器は各製薬会社のMRに依頼すると提供してもらえることが多いです。エアゾール製剤(pMDI)用のスペーサーや、ドライパウダー製剤(DPI)のデモ器など、取り扱っている製品に応じて揃えておくとよいでしょう!
STEP4:指導内容の記録
指導内容は薬歴に記録しておきます。具体的には以下の項目を記録しておくとよいでしょう
- 使用した文書と練習用吸入器の種類
- 患者の吸入手技の状況と問題点
- 指導した内容
- 患者の理解度や習熟度
情報提供文書の写しを薬歴に添付しておくことも有効です。
STEP5:医療機関への情報提供
指導結果等を医療機関に文書で提供します。情報提供の方法は以下の2通りがあります:
- 文書による情報提供: 吸入指導報告書などの専用文書を作成し提供
- お薬手帳による情報提供: お薬手帳に指導内容を記載
お薬手帳による情報提供の場合は、患者さんに次回受診時に医師へお薬手帳を提示するよう伝えることが必要です。
STEP6:算定タイミングの確認
吸入薬指導加算は、吸入指導を行った時点で算定することができます。次回来局時の確認や指導については算定要件には含まれていません。
ただし、3ヶ月に1回という算定制限があるため、前回算定日から3ヶ月以内かどうかを確認する必要があります。例外として、他の吸入薬が処方され別途指導を行った場合は3ヶ月以内でも算定可能です。
吸入薬指導加算のレセプト請求と記載事項

レセプト摘要欄への記載事項
吸入薬指導加算を算定する場合、レセプト摘要欄には以下の内容を記載します
- 吸入薬の調剤年月日: 「吸入薬の調剤年月日;令和○年△月□日」
- 吸入薬の名称: 「吸入薬の名称;○○○○」
異なる吸入薬で3ヶ月以内に再算定する場合は、前回算定日も記載します。

ポッポ先生
レセプト記載は正確に行うことが重要です。例えば、2025年5月10日に「エアゾリンエアゾル100μg」を調剤して吸入薬指導加算を算定した場合は、「吸入薬の調剤年月日;令和7年5月10日」「吸入薬の名称;エアゾリンエアゾル100μg」と記載します!
効果的な吸入指導のポイント

吸入デバイス別の指導ポイント
吸入薬にはさまざまなデバイスがあり、それぞれ使用方法が異なります。主なデバイスとその指導ポイントを紹介します。
1. pMDI(定量噴霧式吸入器)
- 使用前に十分に振ること
- 吸入口から約3cm離して保持すること
- ゆっくりと深く息を吐いた後、吸入開始と同時に噴射すること
- 噴射後、約5秒間息を止めること
- スペーサーの使用を推奨(特に高齢者や小児)
2. ドライパウダー吸入器(DPI)
- 湿気を避けること
- デバイス内に薬剤をセットしたら水平を保つこと
- 強く深く吸入すること
- 吸入後、約5秒間息を止めること
- デバイス内に息を吐きこまないこと
3. ソフトミスト吸入器(SMI)
- 初回使用時や長期間使用していない場合は空打ちが必要
- 吸入口をしっかりと咥えること
- ゆっくりと深く息を吸いながらボタンを押すこと
- 吸入後、約5秒間息を止めること
年齢層別の指導ポイント
小児への指導
- 保護者同伴で指導を行う
- 年齢に応じたデバイスの選択を確認
- スペーサーの使用を推奨
- 理解度に応じた説明と繰り返しの指導
高齢者への指導
- 手指の力や肺活量の低下を考慮
- 操作が簡単なデバイスを選択するよう提案
- 視力低下を考慮した文字の大きい説明資料の使用
- 吸入手技を繰り返し確認
患者さんが正しく使えているか確認するポイントはありますか?

オカメインコ

ポッポ先生
良い質問です!以下のような点に注意して確認するとよいでしょう
- 吸入器の準備手順が正確か
- 息を十分に吐き出しているか
- 吸入のタイミングと吸気の強さは適切か
- 吸入後に息止めができているか
- 複数回吸入する場合、適切な間隔を空けているか 特に高齢者では、握力低下でデバイス操作が難しい場合があるので、実際に操作してもらい確認するのが重要です!
吸入薬の副作用と対策
主な副作用
- 局所的副作用
- 口腔カンジダ症
- 嗄声
- 咽頭刺激感
- 咳嗽
- 全身性副作用
- 頻脈
- 振戦
- 低カリウム血症
- 高血糖
副作用対策
- ステロイド吸入薬使用後の含嗽を徹底
- スペーサーの使用による口腔内沈着の軽減
- 副作用出現時の対応方法の説明
- 定期的な副作用モニタリングの重要性
情報提供文書の作成ポイント

記載すべき内容
医療機関への情報提供文書には、以下の内容を簡潔に記載するとよいでしょう
- 患者基本情報:氏名、年齢、吸入薬の処方内容
- 吸入指導の内容:使用した文書、デモ器の種類
- 患者の手技評価:良好な点、問題点
- 指導した内容:具体的な指導ポイント
- 患者の理解度:十分に理解できているか、定期的な確認が必要か
- 薬剤師からの提案:必要に応じて、デバイス変更や補助器具の使用など
効果的な情報提供のコツ
- 簡潔に要点をまとめる
- チェックリスト形式を活用し、記入の手間を削減
- 医師が求める情報(治療効果や治療継続の判断材料)を優先的に記載
- デバイスごとの評価表を活用

ポッポ先生
情報提供文書は「指示」ではなく「情報提供と提案」であることを意識した表現を心がけましょう。医師が次の診療時に役立てられる内容を、簡潔かつ要点を押さえて伝えることが重要です!
吸入薬指導加算の算定事例

事例1:初回指導の場合
65歳男性、喘息で初めてフルティフォーム(pMDI)が処方。医師から吸入指導の依頼あり。文書とデモ器を用いて基本的な吸入手技を指導。スペーサー使用を提案し、医療機関に情報提供。翌月の処方箋受付時に吸入薬指導加算を算定。
事例2:デバイス変更時の再指導
72歳女性、COPDでシムビコート(タービュヘイラー)からエンクラッセ(エリプタ)へ変更。デバイスが異なるため、新たに文書とデモ器を用いて吸入手技を指導。前回の吸入薬指導加算から2ヶ月だが、異なる吸入薬のため再算定可能。
事例3:かかりつけ薬剤師による指導
58歳男性、かかりつけ薬剤師指導料を算定中の患者。喘息でレルベア(エリプタ)が処方され、吸入手技に不安あり。2024年度改定後はかかりつけ薬剤師指導料と吸入薬指導加算の併算定が可能となったため、指導後に両方を算定。
吸入薬指導に役立つツールと資材

製薬会社提供の資材
各製薬会社は以下のような吸入指導用の資材を提供しています
- 製品別の吸入手技説明書
- 練習用吸入器(デモ器)
- 患者用の吸入手技チェックリスト
- 動画教材
MRに依頼すれば入手可能なものが多いので、積極的に活用しましょう。
自作ツールの活用
薬局独自の吸入指導ツールを作成することも効果的です
- 吸入手技評価シート
- 患者向け説明資料
- 吸入指導記録フォーム
- 医療機関への情報提供文書テンプレート
Google スプレッドシートなどを活用して効率的に作成・記録できるようにしておくと便利です。
患者さんへの説明で工夫すべき点はありますか?

オカメインコ

ポッポ先生
患者さんの理解度に合わせた説明が大切です!高齢者には大きな文字と簡潔な表現で、難しい医学用語は避けましょう。また、「なぜその手順が重要なのか」という理由も併せて説明すると理解が深まります。写真や動画を活用すると更に効果的ですよ!
まとめ:吸入薬指導加算の活用と今後の展望

吸入薬指導加算は、患者さんの吸入薬使用の質を高め、治療効果の向上に貢献するための重要な評価項目です。30点という点数は決して高くありませんが、患者さんの治療アウトカム改善という意義と、地域支援体制加算の実績要件に含まれる重要性を考えると、積極的に取り組むべき業務といえるでしょう。
2024年度改定でかかりつけ薬剤師指導料との併算定が可能になったことで、かかりつけ薬剤師による継続的な吸入指導の価値が認められました。今後も薬剤師の専門的な介入が評価され、患者さんの治療効果向上に貢献する機会が増えていくことが期待されます。
吸入薬の正しい使用は、喘息やCOPDの治療成功のカギとなります。薬剤師として専門性を発揮し、患者さん一人ひとりに合わせた丁寧な指導を行うことで、患者さんのQOL向上と医療費の適正化に貢献していきましょう。

ポッポ先生
最後に一言!吸入薬指導は「加算を取るため」ではなく「患者さんの治療効果を高めるため」に行うものです。指導を通じて患者さんとの信頼関係が深まり、他の薬物治療への介入機会にもつながります。ぜひ積極的に取り組んでみてください!