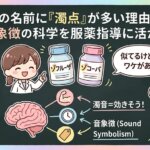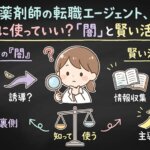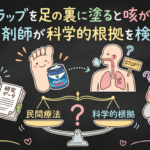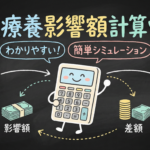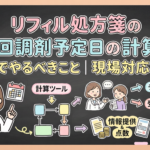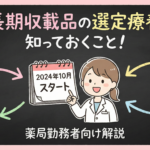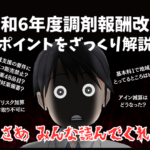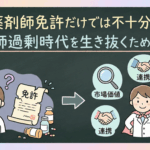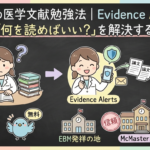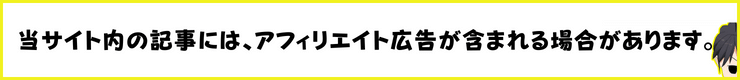2024年度の診療報酬改定で、これまでの「調剤後薬剤管理指導加算」が「調剤後薬剤管理指導料」として独立した薬学管理料に格上げされました。対象疾患も拡大され、薬局薬剤師の服薬期間中のフォローアップがますます重要視されています。
この記事では、調剤後薬剤管理指導料の概要、算定要件、実践のポイントを解説し、忙しい薬局業務の中でも効率的に算定できるヒントをお伝えします。
目次
調剤後薬剤管理指導料とは?改定のポイントを解説

調剤後薬剤管理指導料は、対象患者さんが治療薬を適正に使用できるよう、医療機関と薬局が連携してサポートを行った場合に算定できる薬学管理料です。2024年度の診療報酬改定により、従来の「調剤後薬剤管理指導加算」から単独の薬学管理料として新設されました。

ポッポ先生
調剤後薬剤管理指導料は、2019年の改正薬機法で義務化された「服薬期間中のフォローアップ」を評価する診療報酬として、中核的な位置づけになっています!対象疾患の拡大は、薬剤師の関与で患者アウトカムが改善する可能性が評価された結果と言えますね。
主な改定ポイント
- 名称の変更: 「調剤後薬剤管理指導加算」から「調剤後薬剤管理指導料」へ
- 対象疾患の拡大:
- 糖尿病(全ての糖尿病治療薬が対象に)
- 慢性心不全(新規追加)
- かかりつけ薬剤師指導料との併算定:
- 以前はできなかったが、2024年度改定から可能に
糖尿病に関しては、以前はインスリン製剤またはスルフォニル尿素系製剤(SU剤)を使用している患者さんのみが対象でしたが、改定後は全ての糖尿病治療薬が対象となりました。また、新たに慢性心不全患者さんも対象に加わったことで、薬剤師の介入による貢献の場が広がりました。
なぜ糖尿病と心不全が対象なんですか?他の生活習慣病は対象じゃないんですか?

オカメインコ

ポッポ先生
いい質問ですね!糖尿病と心不全は服薬アドヒアランスや生活管理が特に重要で、薬剤師の介入効果が高いとされています。また、地域包括診療料の対象疾患とも整合性を持たせる意図もあるようです。将来的には他の疾患も対象になる可能性はありますよ。
調剤後薬剤管理指導料の点数と算定要件

点数
- 調剤後薬剤管理指導料1(糖尿病): 60点(月1回まで)
- 調剤後薬剤管理指導料2(心不全): 60点(月1回まで)
両方の要件を満たせば、同一月に両方を算定することも可能です。
基本的な算定要件
調剤後薬剤管理指導料を算定するには、以下の要件をすべて満たす必要があります:
- 施設基準: 地域支援体制加算の届出を行っている薬局であること
- 対象患者:
- 指導料1:糖尿病治療薬が処方されている患者
- 指導料2:心疾患による入院歴があり、作用機序の異なる複数の循環器疾患治療薬が処方されている慢性心不全患者
- 業務内容:
- 医師の指示または患者の求めに応じて、調剤後に電話等により薬剤の使用状況、副作用の有無等を確認
- 確認された情報に基づき、必要な薬学的管理指導を実施
- 薬学的管理指導の結果を医療機関に文書で情報提供
- 記録: 情報提供した文書の写しまたはその内容の要点を薬歴に添付・記載
調剤した日に電話して確認しても算定できるんですか?

オカメインコ

ポッポ先生
いいえ、調剤と同日に電話等で使用状況確認を行った場合は算定できません。服薬期間中のフォローアップという趣旨ですので、調剤日と別の日に確認を行う必要があります!
糖尿病患者への調剤後薬剤管理指導料1の算定ポイント

調剤後薬剤管理指導料1は、以下のいずれかに該当する糖尿病患者さんが対象です:
- 新たに糖尿病治療薬が処方された患者さん
- 既に糖尿病治療薬を使用している患者さんで、新たに他の糖尿病治療薬が処方された患者さん
- 糖尿病治療薬の用法・用量の変更があった患者さん
改定前はインスリン製剤またはSU剤に限定されていましたが、改定後はDPP-4阻害薬、SGLT2阻害薬、GLP-1受容体作動薬など、あらゆる糖尿病治療薬が対象となりました。
実践ポイント
- 新規処方や用法用量変更があった患者さんをシステムで抽出できるようにしておく
- 処方せん受付時に対象患者をチェックするフローを確立する
- フォローアップ実施日の目安を患者さんと相談して決めておく
- 低血糖リスクに加え、各薬剤特有の副作用症状も確認項目に入れる

ポッポ先生
糖尿病治療薬は種類によって特徴的な副作用が異なります。SGLT2阻害薬であれば性器感染症や脱水、GLP-1受容体作動薬であれば消化器症状など、薬剤ごとの確認ポイントを整理しておくと効率的ですよ!
慢性心不全患者への調剤後薬剤管理指導料2の算定ポイント

調剤後薬剤管理指導料2は、以下の条件を満たす慢性心不全患者さんが対象です:
- 心疾患による入院歴がある
- 作用機序の異なる複数の循環器疾患治療薬が処方されている
具体的な治療薬としては、以下のような薬剤が考えられます:
- ARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)
- ACE阻害薬
- β遮断薬
- SGLT2阻害薬
- ARNI(アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬)
- 利尿薬
- などの併用療法
実践ポイント
- 入院歴の確認が必要(お薬手帳や患者インタビューで情報収集)
- 複数の循環器疾患治療薬の確認(作用機序が異なる薬剤の確認)
- 体重増加、むくみ、息切れなどの症状悪化兆候の確認
- 塩分・水分制限などの生活指導も重要
SGLT2阻害薬は糖尿病薬でもあり、心不全治療薬でもありますよね。両方の病気がある患者さんはどうなるんですか?

オカメインコ

ポッポ先生
鋭い質問です!慢性心不全の治療に用いられることのある糖尿病用薬(SGLT2阻害薬など)が処方されているだけでは、単純に両方の加算を取ることはできません。糖尿病と心不全の両方の診断があり、それぞれの算定要件を満たす場合に限り、両方を算定できます。
効率的な運用のためのフローチャート

調剤後薬剤管理指導料の算定を日常業務に組み込むためのフローの一例です
- 処方箋受付時: 対象疾患・薬剤のスクリーニング
- 初回指導時: フォローアップ実施予定日の設定と患者同意の取得
- フォローアップ前: 確認項目リストの作成
- フォローアップ実施: 電話等での状況確認と指導
- 記録と情報提供: 結果の薬歴記載と医療機関への文書提供
- 評価: 次回のフォローアップ計画立案
各ステップで工夫すべきポイントは以下の通りです:
1. 処方箋受付時のスクリーニング
- 新規処方や用法用量変更などのアラートシステムの活用
- 慢性心不全患者情報の管理リスト作成
2. 初回指導時の工夫
- フォローアップの趣旨説明と同意取得
- 患者の生活リズムに合わせた連絡希望日時の確認
- 確認事項の説明と記録用紙の提供
3-5. フォローアップ実施から記録まで
- 標準的な質問項目リストの作成
- トレーシングレポートのテンプレート準備
- 医療機関への情報提供方法の効率化

ポッポ先生
フォローアップの結果、医師への情報提供が必要な場合は、単に文書を渡すだけでなく、必要に応じて電話で補足説明するなど、真の連携を心がけましょう!それが患者さんの治療効果向上につながります。
トラブルシューティング:よくある疑問と対応策

Q1: 服薬情報等提供料との違いは?
A: 服薬情報等提供料は幅広い患者さんが対象ですが、調剤後薬剤管理指導料は糖尿病や慢性心不全患者さんに特化しています。また、調剤後薬剤管理指導料の方が点数が高く(60点)、医師の指示または患者の求めに応じて行う点が異なります。
Q2: かかりつけ薬剤師指導料算定患者でも算定可能?
A: 2024年度改定により、かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者さんでも、要件を満たせば調剤後薬剤管理指導料を算定できるようになりました。
Q3: 特別調剤基本料算定薬局での取り扱いは?
A: 特別調剤基本料Aの薬局では一部算定可能ですが、特別調剤基本料Bの薬局では算定できません。
Q4: 情報提供先が敷地内医療機関の場合は?
A: 情報提供先が特別な関係を有する医療機関(敷地内薬局→敷地内医療機関)の場合は算定できません。
フォローアップした結果、特に問題がなかった場合でも医療機関に文書で情報提供する必要があるんですか?

オカメインコ

ポッポ先生
はい、問題がなかった場合でも情報提供が必要です!「問題なく服薬できている」という情報も医師にとっては重要なフィードバックになります。また、医療機関との連携強化という観点からも定期的な情報共有は大切です。
まとめ:薬剤師として調剤後薬剤管理指導料を活用するために

調剤後薬剤管理指導料は、単に算定して収益につなげるだけでなく、患者さんの治療効果向上と医療機関との連携強化という本質的な目的があります。
糖尿病や慢性心不全は服薬アドヒアランスや生活管理が特に重要な疾患です。薬剤師が調剤後のフォローアップに積極的に関わることで、副作用の早期発見や症状悪化の予防、適切な服薬支援につながります。
2024年度の診療報酬改定を機に、改めて調剤後の患者フォローの重要性を認識し、日常業務に組み込んでいきましょう。患者さんの健康に貢献するという薬剤師本来の使命に立ち返り、このような制度を有効活用することが求められています。

ポッポ先生
調剤後薬剤管理指導料の算定は単なる事務作業ではなく、薬剤師の専門性を活かした臨床業務です。患者さんとの信頼関係構築と医療の質向上につながる重要な業務として位置づけ、積極的に取り組んでいきましょう!