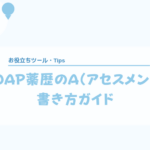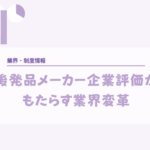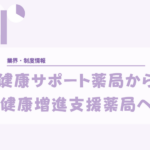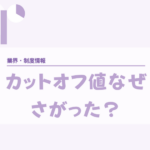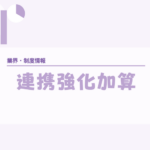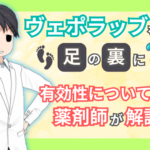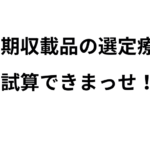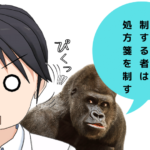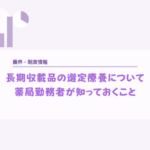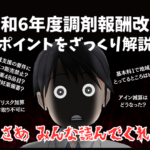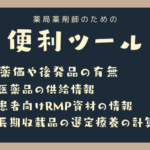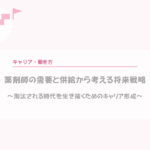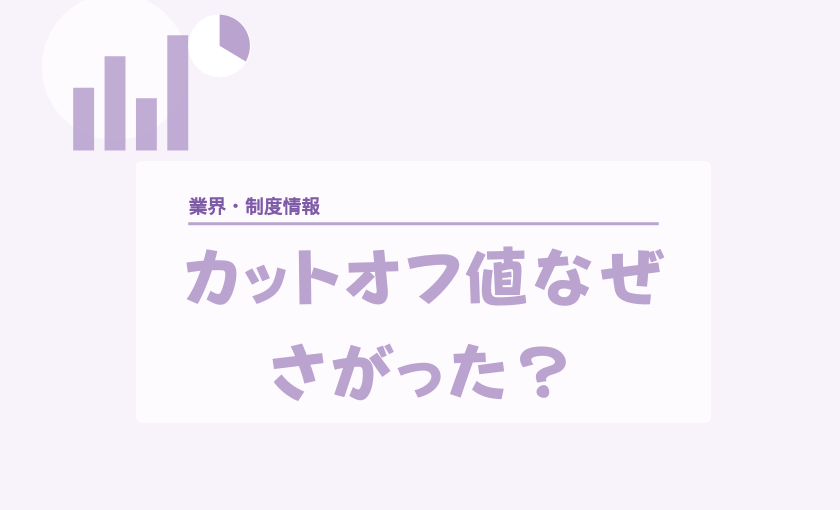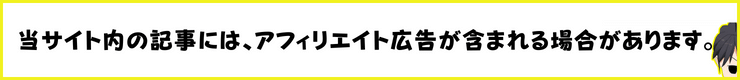2025年4月以降、多くの薬局で後発医薬品調剤体制加算の要件であるカットオフ値が急激に下がり、薬局経営に大きな影響を与えています。カットオフ値が50%を下回ってしまうと、後発医薬品の置き換え率が90%以上という高い水準を維持していても、加算を算定することができなくなってしまいます。
このような状況が突然発生した背景には、2025年4月の薬価改定による薬価基準収載品目リストの分類変更があります。今回は、なぜカットオフ値が急激に下がったのか、その仕組みと対応策について、わかりやすく解説していきます。
目次
カットオフ値とは?基本的な仕組みを理解しよう
まず、カットオフ値の計算方法を確認しましょう。カットオフ値は以下の式で算出されます
カットオフ値 = (後発医薬品のある先発医薬品+後発医薬品の規格単位数量)÷ 全薬剤の規格単位数量
カットオフ値は、当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量のうち、後発医薬品のある先発医薬品と後発医薬品を合算した規格単位数量の占める割合を示しています。

ポッポ先生
カットオフ値は、薬局で取り扱う全ての薬剤のうち、後発医薬品に置き換え可能な薬剤がどの程度の割合を占めているかを表す指標です。この値が高いほど、後発医薬品への取り組みがしやすい環境にあると言えますね。
なるほど!つまり、分子が小さくなったり分母が大きくなったりすると、カットオフ値は下がってしまうということですね?

オカメインコ
2025年薬価改定で何が変わった?分類の変更が鍵
2025年の薬価改定では、薬価基準収載品目リストの分類が大幅に見直されました。
- 1:後発品がない先発品
- 2:後発品がある先発品
- 3:後発品
- 空欄:昭和42年以前承認医薬品及び基礎的医薬品
- ☆:後発品と同額又は薬価が低い先発品
- ★:先発品と同額又は薬価が高い後発品
影響を受けた代表的な薬剤例
今回の薬価改定により、以下のような薬局でよく取り扱われる薬剤が「☆」「★」に分類され、カットオフ値の分子から除外されるようになりました
- ロキソプロフェンナトリウムテープ(ロキソニンテープ)
- カルボシステイン(ムコダイン)
- ドンペリドン(ナウゼリン)
- モサプリドクエン酸塩(ガスモチン)
- グリメピリド(アマリール)
- ビソプロロールフマル酸塩(メインテート)
カットオフ値急降下の仕組み:分子の減少が主因
カットオフ値が急激に下がった最大の要因は、分子となる「後発医薬品のある先発医薬品と後発医薬品を合算した規格単位数量」が減少したことです。
2025年3月まで
- 分子:「2」+「3」の薬剤
- 分母:全薬剤
2025年4月以降
- 分子:「2」+「3」の薬剤が「☆」「★」に(分子から除外)
- 分母:全薬剤

ポッポ先生
今まで分子でカウントしていた「2」や「3」に分類される薬剤が、「☆」や「★」に再分類されることで、計算式の分子から外れてしまうんです。これがカットオフ値低下の直接的な原因ですね。
具体的な影響:90%達成でも加算算定不可の事態
後発医薬品調剤体制加算の施設基準では、カットオフ値50%以上という要件があります。この要件を満たさない場合、以下のような深刻な影響が生じます
後発医薬品調剤体制加算の点数
- 加算1:21点(後発品割合80%以上)
- 加算2:28点(後発品割合85%以上)
- 加算3:30点(後発品割合90%以上)
いくら後発医薬品の置き換え率が90%を超えていても、カットオフ値が50%を下回ると、これらの加算をまったく算定できなくなってしまいます。
せっかく頑張って後発医薬品の使用率を上げても、カットオフ値が低いと意味がないなんて…!薬局の経営にとって大きな打撃ですよね。

オカメインコ
厚労省による救済措置:臨時的取り扱いの活用
厚生労働省は、この状況を受けて2024年5月から救済特例措置を実施しています。この措置により、以下の対応が可能となりました
臨時的取り扱いの内容
- 分子への特定医薬品の追加計算が可能
- 1か月単位での適用ができる
- 直近3か月の期間中での混在適用も認められる
2025年度についても、この救済措置は継続され、薬価中間年改定を踏まえて対象薬剤の見直しが行われています。

ポッポ先生
この臨時的取り扱いを活用することで、多くの薬局がカットオフ値の要件を満たし、加算の算定を継続できるようになっています。該当する薬局は積極的に活用を検討しましょう!
薬局での実践的対応策
1. 現状把握の徹底
- 自局のカットオフ値を正確に算出
- 臨時的取り扱い適用前後での比較検討
- 月次でのモニタリング体制の構築
2. 届出手続きの適切な実施
- 施設基準通知に従った新規届出または辞退手続き
- 臨時的取り扱いを反映した割合での記載
- 地方厚生(支)局への適切な申し出
3. 薬剤管理の最適化
- 「☆」「★」分類薬剤の把握と管理
- 後発医薬品採用戦略の見直し
(★⇒3の後発医薬品に変更するなど) - 処方元へ使用薬剤の調整の依頼
対応策がいろいろあるんですね!でも、これらの情報ってどこで最新版を確認すればいいんですか?

オカメインコ
4. 情報収集体制の強化
厚生労働省から定期的に更新される「診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目の一覧」及び「カットオフ値の算出に含める品目の一覧」を定期的にチェックしましょう。
まとめ:変化に対応した薬局運営を目指して
2025年4月の薬価改定によるカットオフ値の急降下は、多くの薬局にとって予想外の課題でした。しかし、その仕組みを理解し、厚労省の救済措置を適切に活用することで、この難局を乗り越えることができます。
今すぐ取り組むべきポイント
- 自局のカットオフ値の正確な算出と分析
- 臨時的取り扱いの適用可否の検討
- 必要に応じた届出手続きの実施
- 継続的な情報収集体制の構築

ポッポ先生
薬価改定は毎年行われる重要な制度変更です。今回の経験を活かして、今後も制度変更に迅速に対応できる体制を整えておくことが大切ですね。患者さんへの適切な医療提供と薬局の安定経営の両立を目指しましょう!
後発医薬品調剤体制加算は、後発医薬品の使用促進という政策目標と薬局経営の両方に関わる重要な制度です。制度の変化に適切に対応しながら、患者さんにとって最適な薬物療法を提供し続けていきましょう。